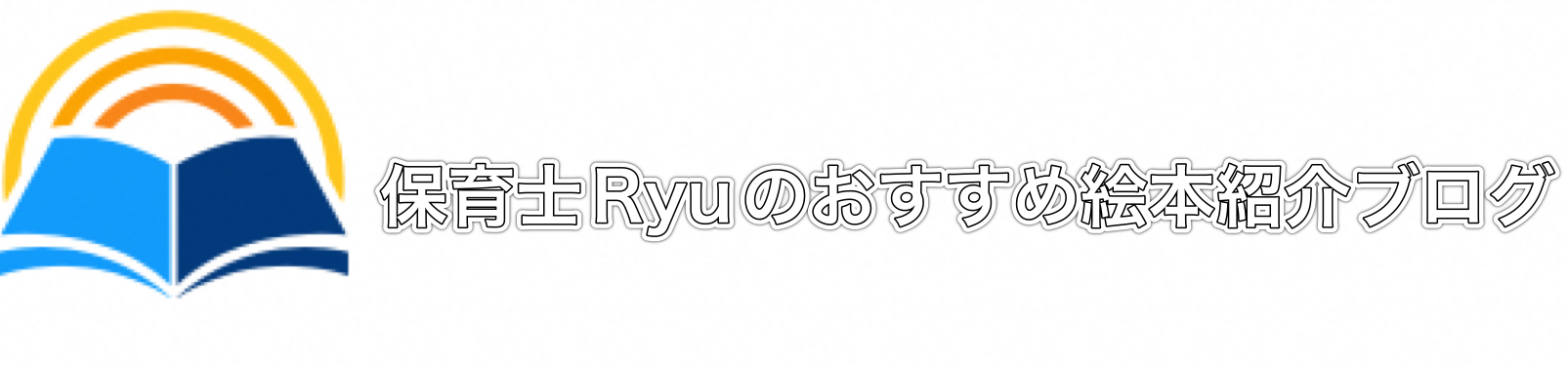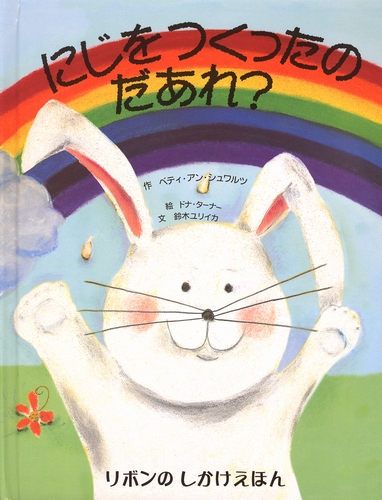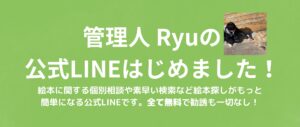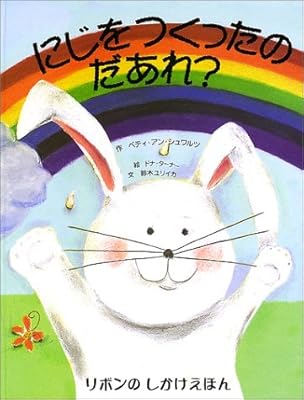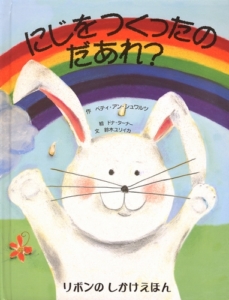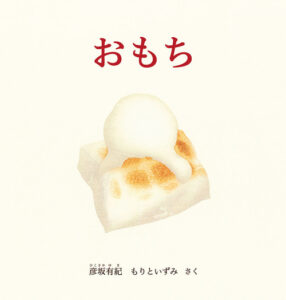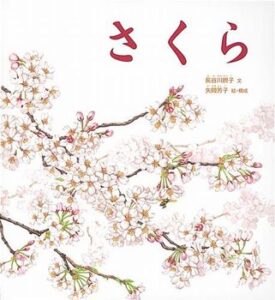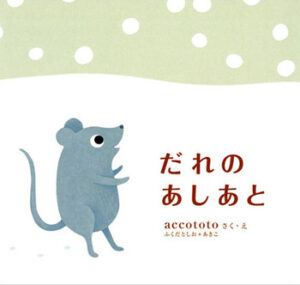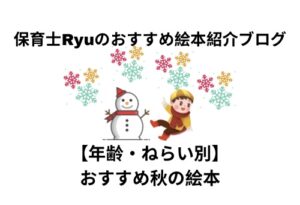【2,3歳児おすすめ絵本】にじをつくったのだあれ リボンのしかけえほん【ねらい・読み聞かせのポイント教えます】
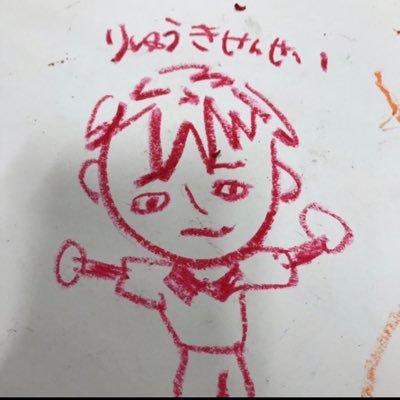 Ryu
Ryu「にじをつくったのだあれ」は私が”色に関心を示して欲しい””自然現象に関興味を持って欲しい”というねらい・想いを持って読むことが多い一冊です。
保育士歴10年以上のRyuが日本一詳しいレビューをお届けします。
- 色の名前を覚え、興味を持つ
- 虹などの自然現象に関心を抱く
- リボンに触れ感触を楽しむ
作品紹介
| 作 | ベティ・アン・シュワルツ |
| 絵 | ドナ・ターナー |
| 文 | 鈴木 ユリイカ |
| 出版社 | 世界文化社 |
| 発行日 | 2002/9 |
| 値段 | ¥1760 |
| 大きさ・ページ数 | 29.6×22.5cm/14p |
「にじをつくったのだあれ」はこんな絵本!
「にじをつくったのだあれ」ってどんな内容の絵本?
そんな疑問にお答えするために「にじをつくったのだあれ」を簡単にまとめてみました。
- 珍しいリボンの仕掛けが綺麗な仕掛け絵本
- ストーリーの中で様々な色に触れられる
- 虹などの自然現象に興味を持つきっかけになる
まるわかりQ&A
あらすじ・ストーリー・内容
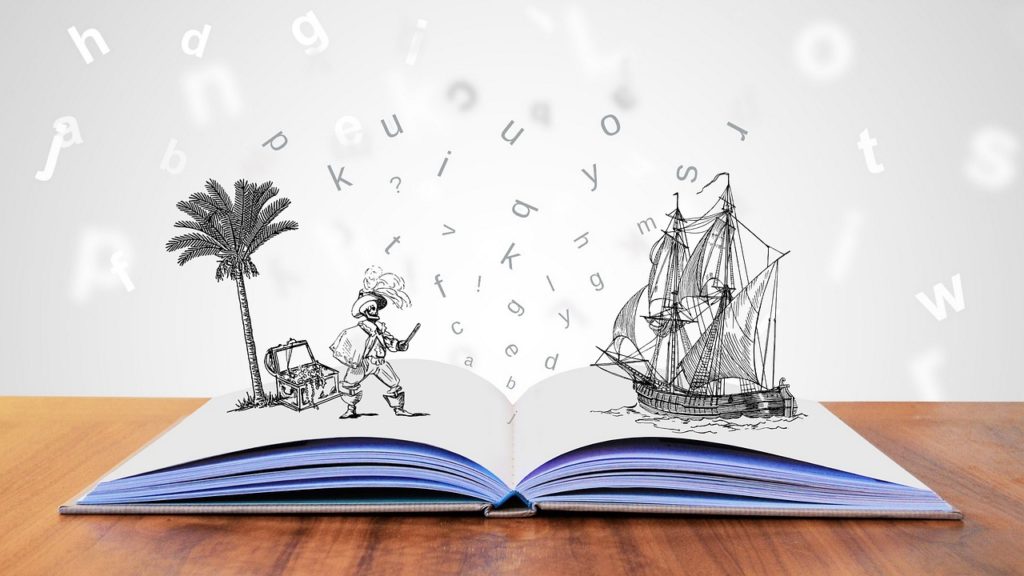
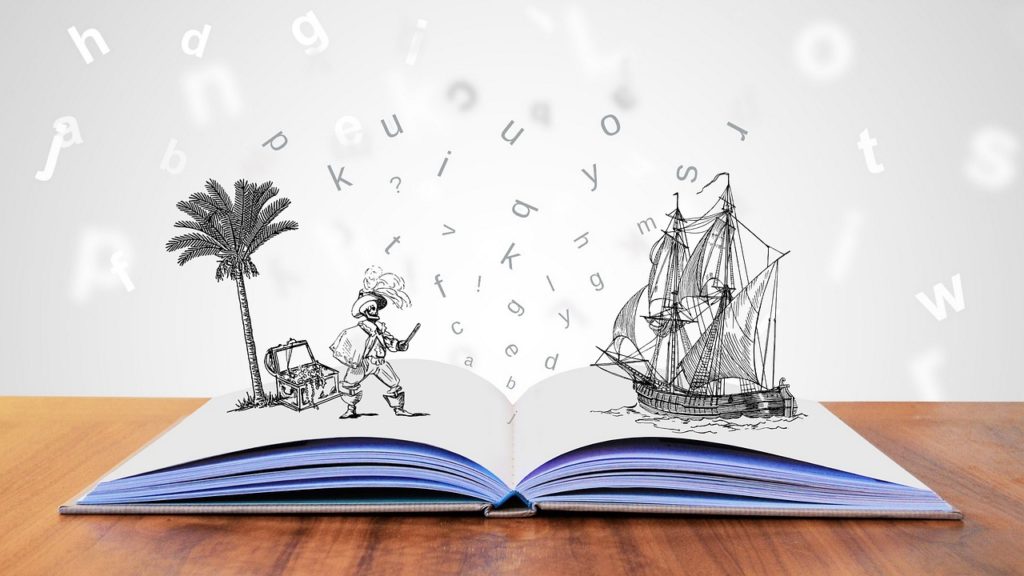
虹を作ったのは誰なのか。うさぎのみみこさんがみんなに尋ねていきます。
おおきな おおきな あかい はな
うさぎの おやこは はなの した
ふたりで たのしい あまやどり
そんな言葉から始まるこの作品。雨が止んだら虹が出てきました。
そこでお母さんに虹を作ったのは誰か聞きます。するとお母さんは「さあね だれかしら? おともだちに きいて ごらん。」
そこから赤、オレンジ、黄色…それぞれの色を誰が作っているのかを虫や生き物に聞いていきます。最後は答えに辿りついたみみこさん。
色彩豊かでリボンと共に楽しめる仕掛け絵本です。
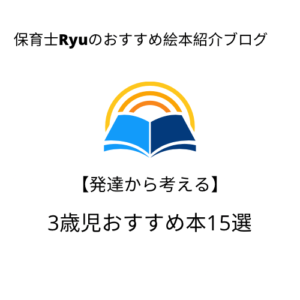
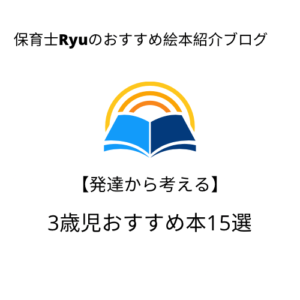
こんな方におすすめ


以下の項目に当てはまる方に「にじをつくったのだあれ リボンのしかけえほん」はぴったりの絵本です!購入を検討してみましょう。
- 色に関する絵本を探している
- 仕掛けがある絵本を探している
絵本比較!あなたに合った絵本を探そう!
「にじをつくったのだあれ リボンのしかけえほん」は探している絵本とは違った…。そんなあなたにはこちらをおすすめ!
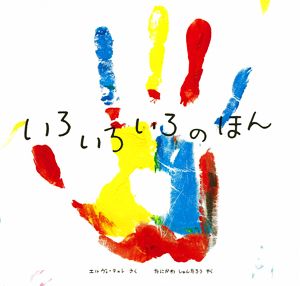
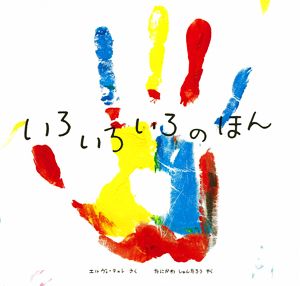
絵本で絵の具遊びが楽しめる?「いろいろいろのほん」
絵の具によって描かれた絵本。それぞれの色が紹介されたり、混ぜたら何色になるのかなどの実験的な遊びが子どもの好奇心をくすぐります。
色の種類や名前を知りながら楽しめる一冊です。


歌を楽しみながら色が覚えられる歌絵本「どんないろがすき」
一定のリズムが繰り返されるとても覚えやすいメロディーが特徴の歌が絵本で楽しめます。それぞれの色に関連したモノも描かれているので、色に関連づけて様々なモノに興味を持つことができます。
色と歌が楽しめる一石二鳥な一冊です。
目的・ねらい


絵本はそれぞれ作者の願いや思いが込められています。その思いを汲み取り、絵本を読むときに目的やねらいを持つ事をおすすめします。以下の「目的・ねらい」はRyuが読み聞かせをするときに大切にしている事です。参考にしてみてください。
- 色の名前や種類を知り、色に関心を示す
- 虹などの自然現象に興味を持つ
目的・ねらい1
色について丁寧に描かれています。
色に関する絵本は多くありますが、「にじをつくったのだあれ リボンのしかけえほん」の特徴はそれぞれの色の名前を3,4回繰り返し書かれているところにあります。
人は反復によって言葉の獲得などをしていくものなので、繰り返し書かれていることで、色の名前が記憶に残りやすいようになっています。
また、赤にも薄い赤や濃い赤、水色に近い青や紺色の海も青として表現されているので色にも様々な種類があり、そのそれぞれに幅があることが理解できるでしょう。
単に色の紹介ではなく、それぞれの色とその色に紐づけられた生き物や食べ物なども一緒に描かれているので、関連づけて覚えることができるようになっています。
目的・ねらい2
自然現象を疑問に思う視点が身につくでしょう。
「にじをつくったのだあれ リボンのしかけえほん」は虹に焦点を当てて描かれています。
子どもにとって虹は身近な存在でありながら、「何故できるのか」は意外と考えたことはない子が多いと思います。
そんな身近な自然現象が何故起こるのかを疑問に感じる場面から物語が始まるので、この絵本を読んだ子も身の回りの現象を疑問に思う新しい視点が生まれるでしょう。
「にじをつくったのだあれ リボンのしかけえほん」の最後には、虹を作るのは雨、7つの色、お日様の光という、しっかりとした根拠も書かれています。
どんなことにも理由があることを感じることができるでしょう。
チェックポイント


現場で毎日読み聞かせを行う現役保育士が、実際に何度も読み聞かせをしたことで分かった大切なポイントを見ていきましょう。
| 年齢 | 2,3歳児頃、特に3歳児 |
| 季節 | 梅雨時期など |
| 行事 | 関係なく楽しめる |
対象年齢
3歳頃がおすすめです。
生活の中で「なぜ?」が増えるこの年齢に読むことで、身の回りのことをもっと知りたいと思う好奇心が芽生えるでしょう。
2歳児でも十分に楽しむことができると思いますが、その場合は色や仕掛けに焦点を当てて読むのがいいでしょう。
時期・季節・行事
様々なことに対して質問をするようになった頃がいいでしょう。
好奇心の芽生えから身の回りのことをたくさん質問する時期が訪れます。そのような様子が見られた時期に読むことで更に好奇心や探求心を深めることができるでしょう。
季節や行事感は特にないので、いつ読んでも大丈夫ですが、雨と関連づけて梅雨の時期に読むのもいいかもしれませんね。
その時には「雨が上がったらお空を見ると虹が出てるかもしれないから、探してみよう」と声を掛けると、絵本からの繋がりも出ておすすめです。
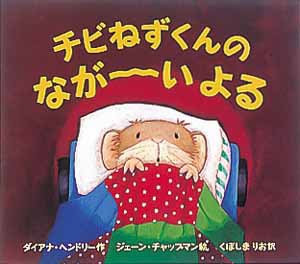
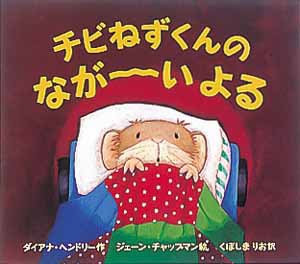
読むときのポイント


「にじをつくったのだあれ」を読み聞かせをする中で意識しているポイントです。読み方を少し意識するだけで内容がぐっと伝わりやすくなります。読み聞かせをする中で自分なりのポイントも探してみるのも面白いですよ。
- それぞれのキャラクターで声色を変えましょう
- 時間を掛け、隅々まで見られるようにしましょう
ポイント1
![]()
![]()
物語のような展開ではないもののそれぞれの色にそれぞれのキャラクターが登場します。
また、キャラクターによって語尾が変わっていたりと個性も感じることができるので、読み分けた方が聞き手としては話が理解しやすくなるでしょう。
読むときの注意としては、「にじをつくったのだあれ リボンのしかけえほん」は「」の記号が使われていないので文面で誰が話しているのかを判断しなければいけません。
初見では少し分かりにくいと思うので、まず初めに目を通してから子どもに読み聞かせをすることをお勧めします。
ポイント2
隅々まで丁寧に描かれている作品です。
絵本の端まで木や花、雲などが描かれていたり、端の色が少し変わっていたりするので、そうした細かい所まで見ることができるように配慮しましょう。
ですが、ゆっくり読む必要はなく、寧ろ会話の部分はテンポよく読んだ方が会話らしく聞こえます。
文を読んだ後に少し空白の時間を空けたり、ページをめくった後に時間を置くなどの工夫をして聞き手が絵や色を十分に楽しんでから文を読むようにしてみるのもおすすめです。また、仕掛けのリボンを触ってもらう時間を設けるのも良いでしょう。
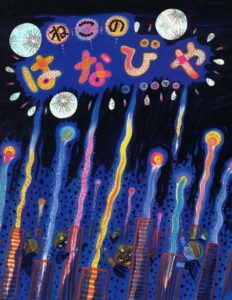
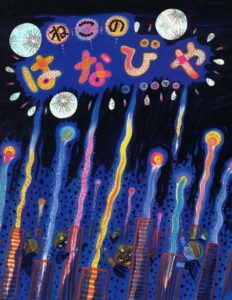
まとめ・Ryuの感想


優しい雰囲気に包まれている仕掛け絵本です。
私は「にじをつくったのだあれ リボンのしかけえほん」の柔らかくて、優しい雰囲気が大好きです。
絵のタッチやうさぎと生き物のやり取り、文の構成などに温もりを感じることができます。
また、それぞれの虹の色が生き物や食べ物、自然物で作られているという発想も素敵で、子どもにとっては本当にそのように感じることができるよう、子どもにも分かりやすい身近なものしか出てきません。
最後には実際の虹の要素を伝えているところも大切で、決して現実離れした話で終わりにすることなく、事実も伝えることは親や保育者の務めでもあります。
「にじをつくったのだあれ リボンのしかけえほん」を読んだ後は、騒がしかった子どもたちもどこか落ち着いた雰囲気になるので、落ち着いてほしいとき、大事な話をする前によく読んでいます。
色や自然現象、生き物の知識を得るだけでなく、心を温めてくれる作品です。
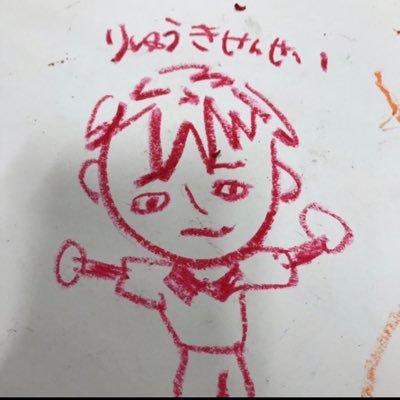
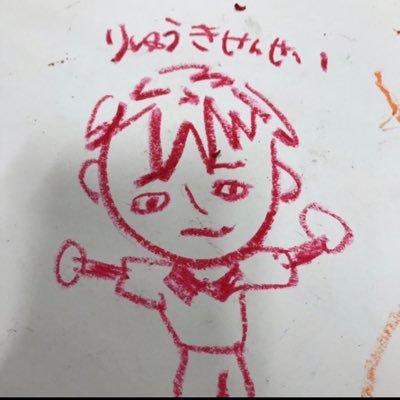
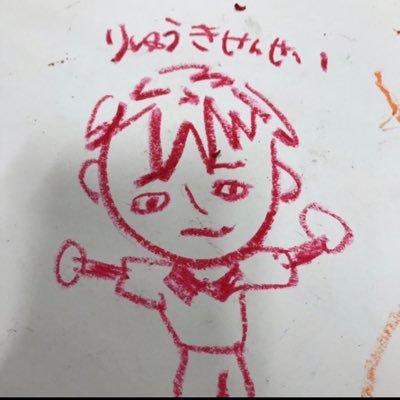
記事を書く励みになります。ポチっとお願いします!