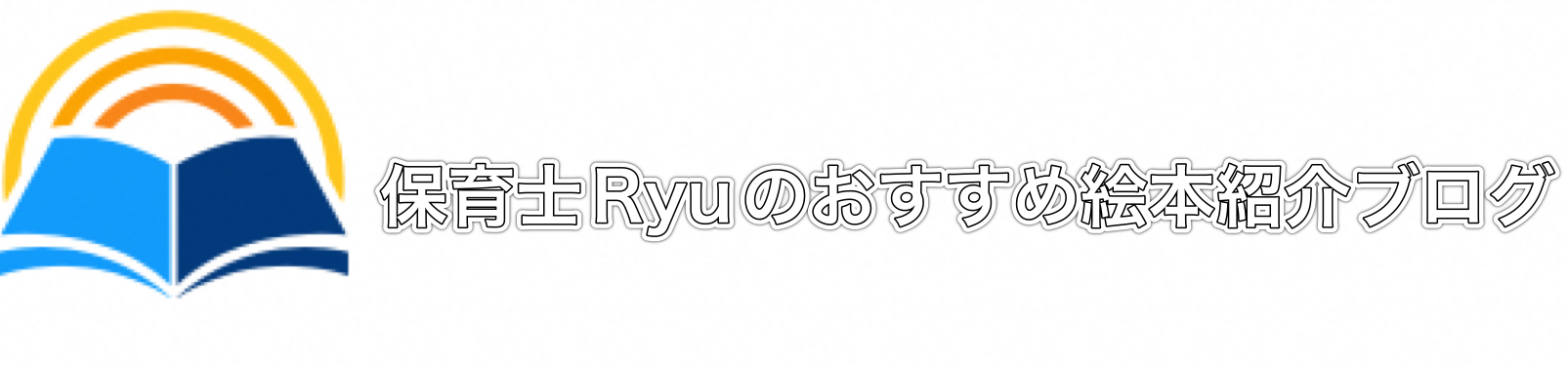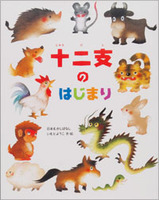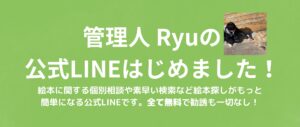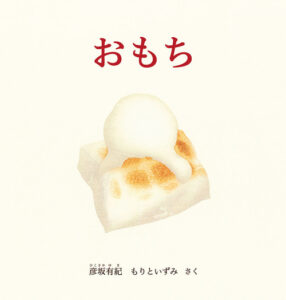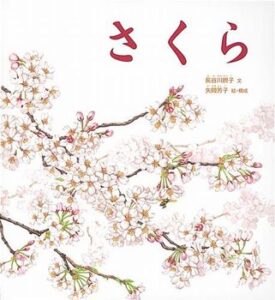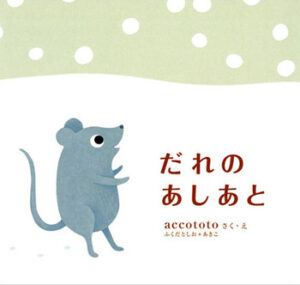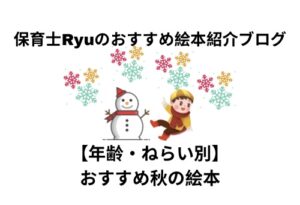【3,4歳児おすすめ絵本徹底レビュー】十二支のはじまり【ねらい・読み聞かせのポイント教えます】
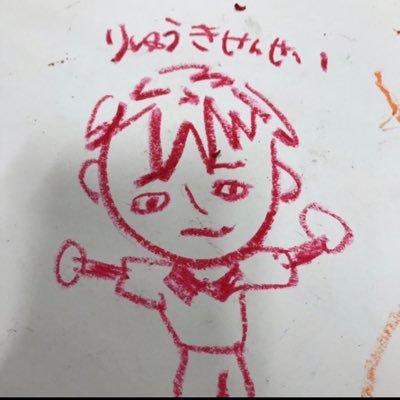 Ryu
Ryu「十二支のはじまり」は私が”十二支の由来を知り、親しみを感じて欲しい””物語とその展開を予測する事を楽しんで欲しい”というねらい・想いを持って読むことが多い一冊です。
保育士歴10年以上のRyuが日本一詳しいレビューをお届けします。
- 十二支の存在を知り、親しみを感じる
- 自分や身近な人の干支を知ろうとする
- ストーリーの展開を予測しながら楽しめる
作品紹介
![]()
![]()
「十二支のはじまり」はこんな絵本!
「十二支のはじまり」ってどんな内容の絵本?
そんな疑問にお答えするために「十二支のはじまり」を簡単にまとめてみました。
- 十二支がどのように決まったかの由来が分かる
- 展開が楽しく、ドキドキワクワクしながら楽しめる
- 昔話だけどいもとようこさんの優しいタッチで子どもも親しみやすい
まるわかりQ&A
あらすじ・ストーリー・内容
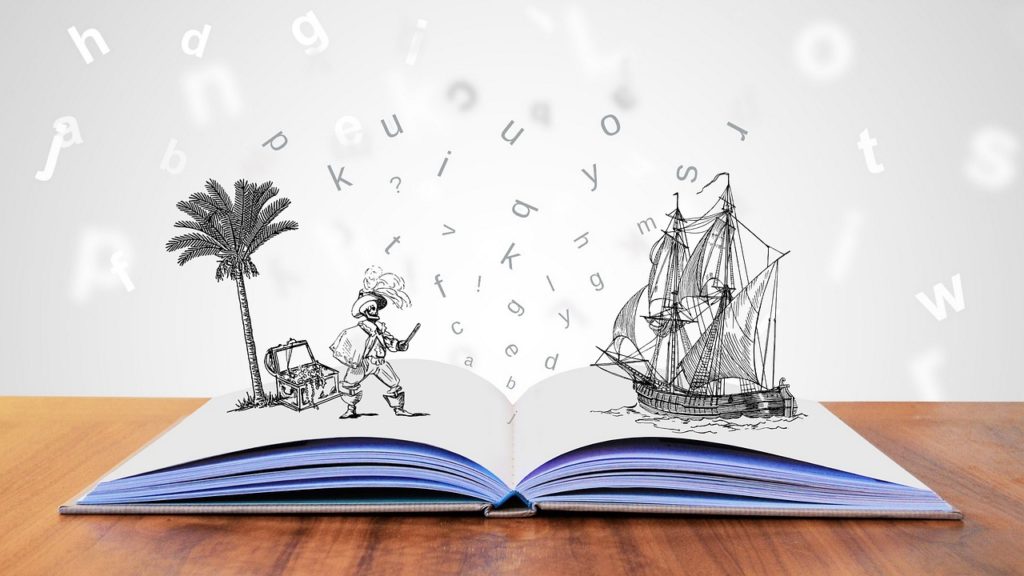
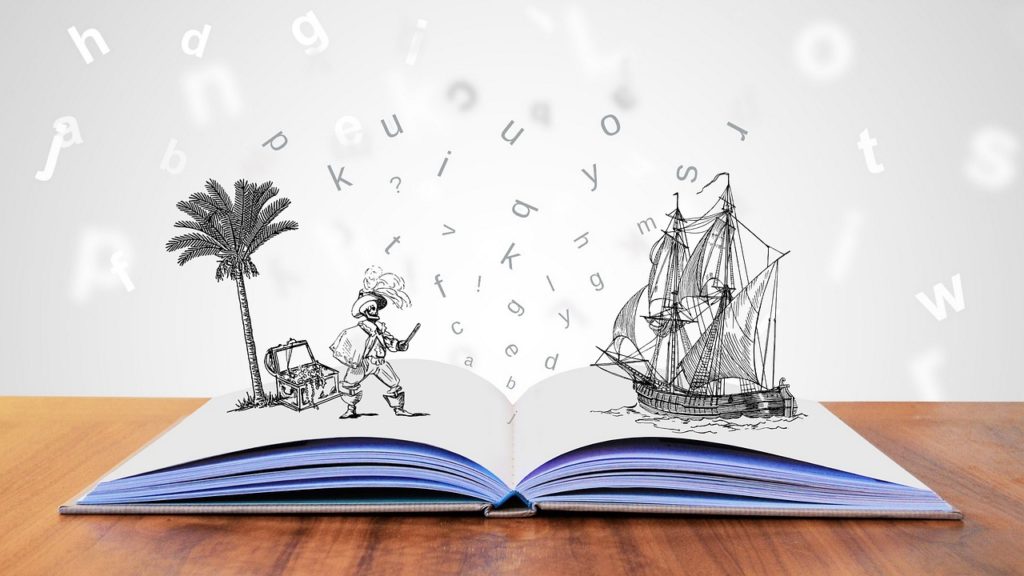
十二支の由来、何故あの順番になったのかが楽しく理解できます。
元日の朝、動物たちの十二支をめぐるかけっこが始まる!
神様が動物たちを集めて「元日の朝、順に来た者から十二番目までの者をその年の大将にする」と伝えます。大将になりたい動物たちは、神様のお家(御殿)に各々向かいます。
遅い牛は暗いうちから、ねずみはその牛の背中に乗って、羊は道草を食いながら、猿と犬は喧嘩をしながら…。そして、最後の猪が到着し、十二支が決定!神様が発表します。
翌日の朝、ねずみに嘘をつかれた猫はのうのうと二日の朝に御殿に向かいます。嘘をつかれた猫はそれ以来ねずみを追いかけるようになったそうですよ。
十二支の物語が面白く・可愛く描かれている作品です。
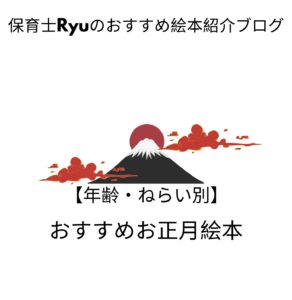
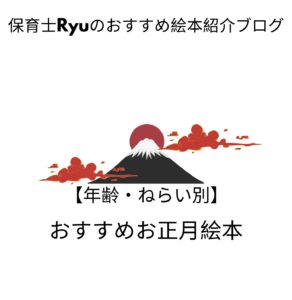
こんな方におすすめ


以下の項目に当てはまる方に「十二支のはじまり」はぴったりの絵本です!購入を検討してみましょう。
- 十二支・正月に関する絵本を探している
- 教養を楽しく伝えられる絵本を探している
絵本比較!あなたに合った絵本を探そう!
「十二支のはじまり」は探している絵本とは違った…。そんなあなたにはこちらをおすすめ!
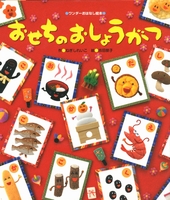
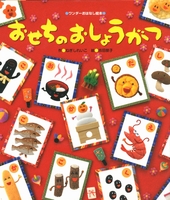
協力・助け合う良さが感じられるストーリー「おせちのおしょうがつ」
おせち料理たちが重箱に乗って鏡餅の家に遊びに行く物語。昆布巻き、海老、金団、ごまめ…様々なおせち料理が登場し、助け合いながら困難を乗り越えていくドキドキのストーリーも魅力的です。
おせち料理を知るきっかけになる一冊です。
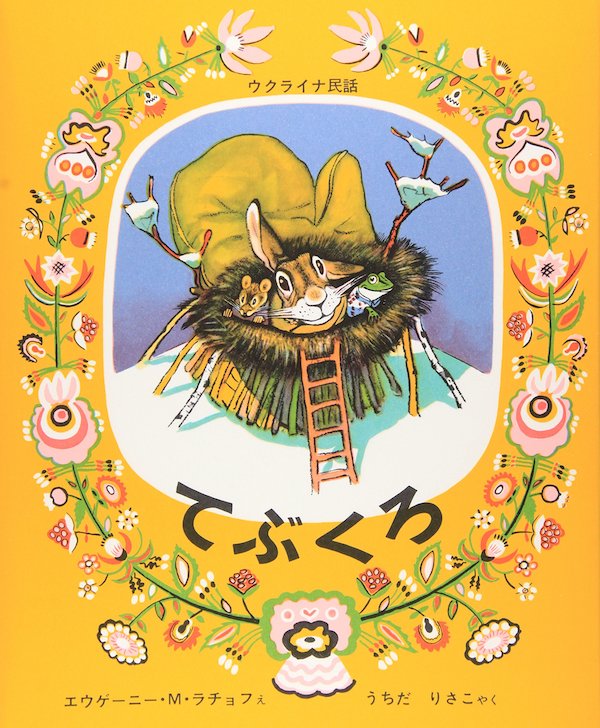
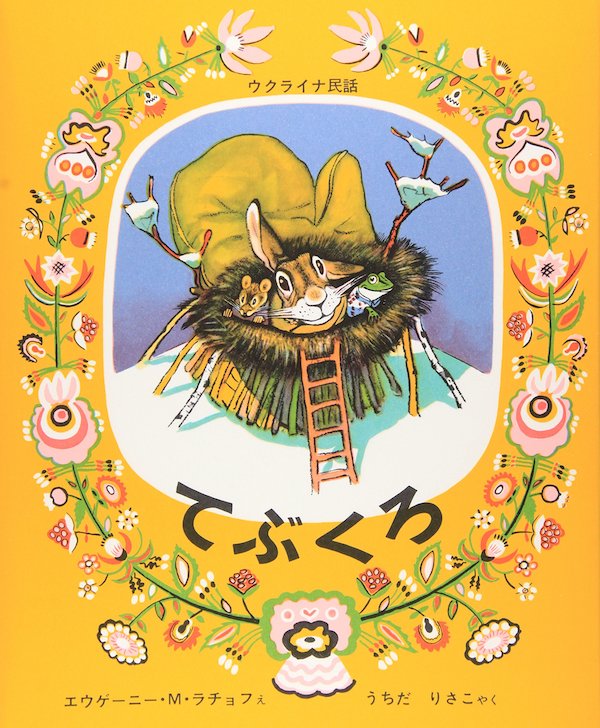
動物たちのやり取りが楽しめる冬に読みたい絵本「てぶくろ」
森の動物たちが落ちているてぶくろに入る為に言葉を交わしていきます。一定のやり取りが楽しく、何度も読みたくなります。
ウクライナ民謡から生まれた傑作本。
会話の楽しさも感じる事ができる一冊です。
目的・ねらい


絵本はそれぞれ作者の願いや思いが込められています。その思いを汲み取り、絵本を読むときに目的やねらいを持つ事をおすすめします。以下の「目的・ねらい」はRyuが読み聞かせをするときに大切にしている事です。参考にしてみてください。
- 十二支について知り、興味を持つ
- 物語の流れを理解し、展開を楽しむ
目的・ねらい1
子どもが知っている動物ばかりなので、親しみを感じることができます。
十二支というと難しいイメージがありますが、その動物のどれもが子どもが知っている動物や生き物です。
子どもからすれば「動物がかけっこをした」という話なので、動物という点から興味を持ちやすくなっています。
十二支を全て覚えるための絵本ではなく、どのような動物が十二支に含まれているのか、どうして十二支が決まったのかをそれとなく理解できれば、それで十分です。
”十二支”という存在があることを、楽しみながら知ることができるでしょう。
目的・ねらい2
次に誰が来るのか…。展開を想像する力が身に付きます。
十二支という存在を知らない子にとっては、次にどの動物が来るのかを想像し、楽しむことができます。
子丑寅…と既に順番を知っている子であっても、どのようにしてその動物の順番が決まったのかを知らない子も多くいるので、順番の決まり方を想像しながら、物語を楽しむことができるでしょう。
動物がかけっこをすることさえ理解できれば、次の展開も想像しやすく、ある程度その後の展開を考えることもできます。
読み手の話を聞きながら次はどうなるのか、誰が来るのかなど、発想豊かに物語を楽しむことができるでしょう。
![]()
![]()
チェックポイント


現場で毎日読み聞かせを行う現役保育士が、実際に何度も読み聞かせをしたことで分かった大切なポイントを見ていきましょう。
| 年齢 | 幼児期、特に4歳児 |
| 季節 | 冬 |
| 行事 | お正月 |
対象年齢
3歳児以降がおすすめです。
動物が出てくることを楽しむのだけであれば2歳児でもギリギリ楽しめそうではありますが、ページ数や文字数を考えると3歳児以降がいいでしょう。
しっかりと内容を把握するのであれば4歳児からがおすすめです。
また、十二支という概念を理解するのは難しいことなので、乳児にはおすすめできません。
時期・季節・行事
物事の因果関係を理解し始めた頃がいいでしょう。
どうして十二支が決まったのかが描かれている作品なので、因果関係を理解できないと、その”どうして決まったのか”が分からず、面白味も半減してしまいます。
季節としては、干支が替わる・替わったお正月前後がいいでしょう。行事としては、お正月に関する会などがあればその時に読むのもいいと思います。
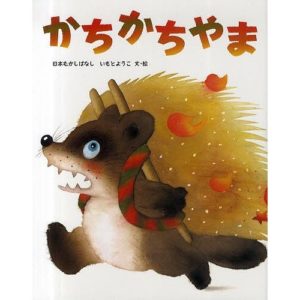
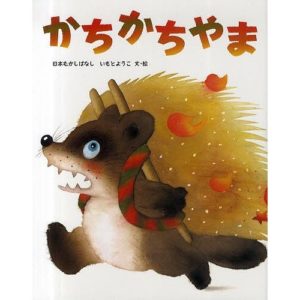
読み聞かせのポイント


「十二支のはじまり」を読み聞かせをする中で意識しているポイントです。読み方を少し意識するだけで内容がぐっと伝わりやすくなります。読み聞かせをする中で自分なりのポイントも探してみるのも面白いですよ。
- 読み手が考えられる間を置きましょう
- 声色を使い分け、状況を理解しやすくしましょう
ポイント1
次にどの動物が来るのかをワクワクさせましょう。
「十二支のはじまり」の楽しみの1つとして、どの動物が何番に来るのかを予想することが挙げられます。
中盤以降は動物たちが、どの順番で、どのように御殿へ到着したのかが描かれているので、そこを読む際には次のページをめくる前に聞き手が次にどの動物が来るのかを想像できるような間を置きましょう。
2,3秒でも置くことで、聞き手が次の展開を考えられるので、次のページをめくるときのワクワク感が違ってきます。
若しくは、「次は誰かな?」とぼやくように言って、聞き手の想像を掻き立てるのももありだと思います。
絵本を楽しめるように読むのは勿論のこと、聞き手の想像力や発想力も育めるように工夫してみましょう。
ポイント2
多くのキャラクターが登場します。声色を少し変えてみましょう。
神様や十二支の生き物たちの他にも猫やカエルなども登場します。
場面ごとにその動物・生き物の絵も描かれているので、誰が話しているのかは分かりやすくなっていますが、声色を少し意識するだけでも聞き手の話の理解がぐっと深まります。
ナレーション部分も多いので、ナレーション部分は淡々と、生き物が話しているときは少し感情を込めて読むことで、物語全体がイキイキとしてくるでしょう。
メリハリをつけることで、聞きやすさに大きな差が生まれます。
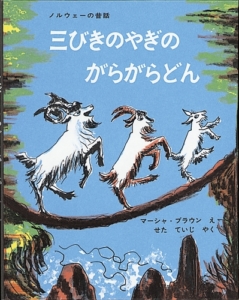
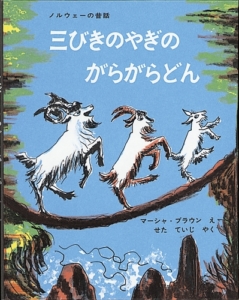
まとめ・Ryuの感想


干支について伝えたいなら、この絵本!
個人的にずっと求めていた一冊でした。「十二支のはじまり」という物語自体は以前から知っていたのですが、まさか私の大好きないことようこさんから出ていたとは。
すぐに購入し、翌日3歳児に読むと大反響!
十二支という言葉や概念は少し難しいと思いましたが、「自分たちの知っている動物たちがかけっこをして、何か順番を決めている」という内容を楽しむことができたようです。
読み終えた後には「面白かった!」「もう一回読んで!」と、好評の嵐。
毎年、お正月の時期には必ず読みたい作品の1つです。
そして、個人的には「十二支のはじまり」と合わせて「子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥」のあのリズムも子どもと一緒に確認すると、絵本の内容も相まって楽しく覚えることができるのでおすすめです。
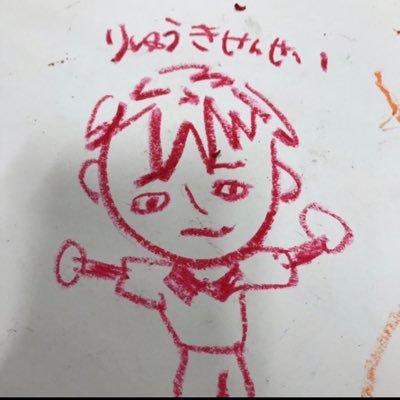
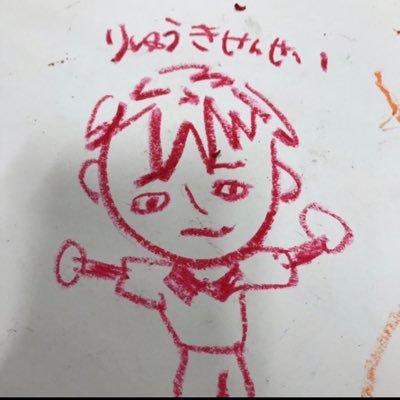
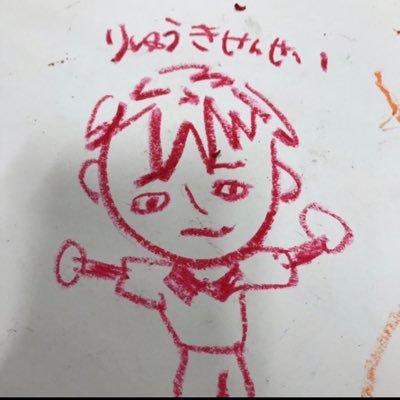
記事を書く励みになります。ポチっとお願いします!