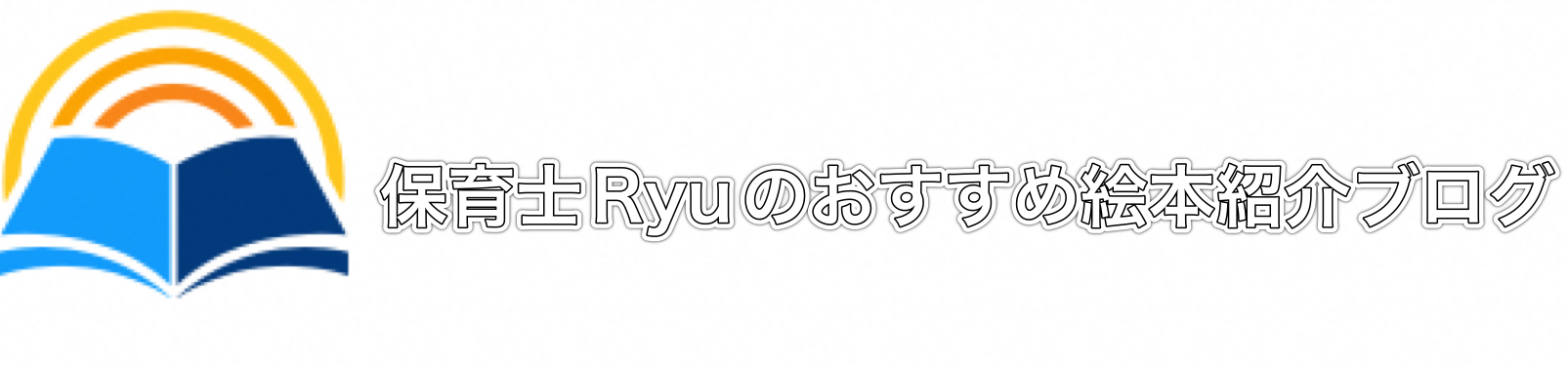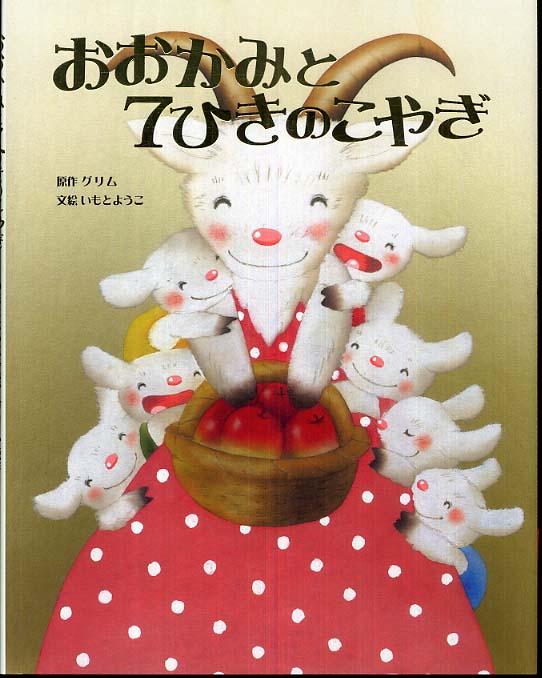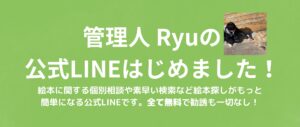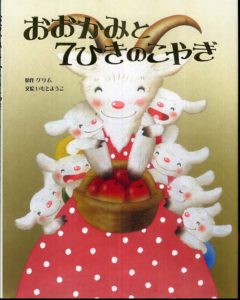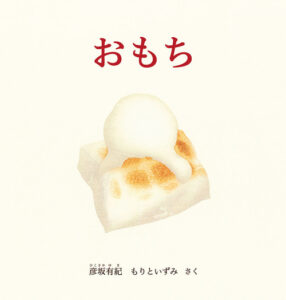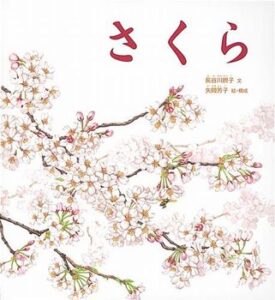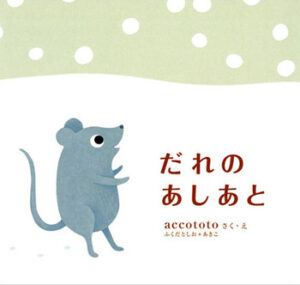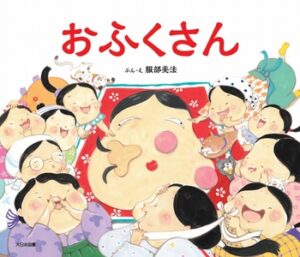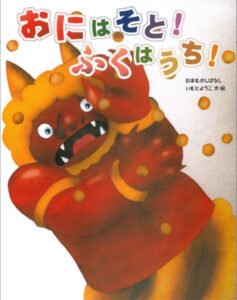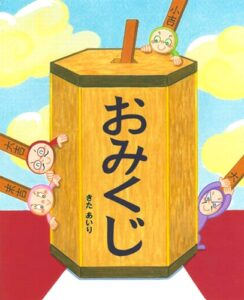【4,5歳児おすすめ絵本】おおかみと7ひきのこやぎ【ねらい・読み聞かせのポイント教えます】
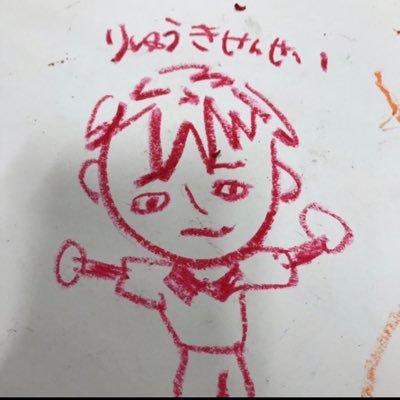 Ryu
Ryu「おおかみと7ひきのこやぎ」は私が”話をよく聞くと良い事もあるということを感じて欲しい””展開を予測しながら楽しみ、ドキドキしながら物語の面白さを感じて欲しい”というねらい・想いを持って読むことが多い一冊です。
保育士歴10年以上のRyuが日本一詳しいレビューをお届けします。
- 話を聞く大切さを感じる
- 物語を楽しいと感じる
- 悪い事をしたら返ってくる事を知る
作品紹介
「おおかみと7ひきのこやぎ」はこんな絵本!
「おおかみと7ひきのこやぎ」ってどんな内容の絵本?
そんな疑問にお答えするために「おおかみと7ひきのこやぎ」を簡単にまとめてみました。
- グリムが原作のドキドキできる作品
- 展開や狼とヤギのやり取りが楽しめる
- 話を聞く大切さ、因果応報などの教訓が感じられる
まるわかりQ&A
あらすじ・ストーリー・内容
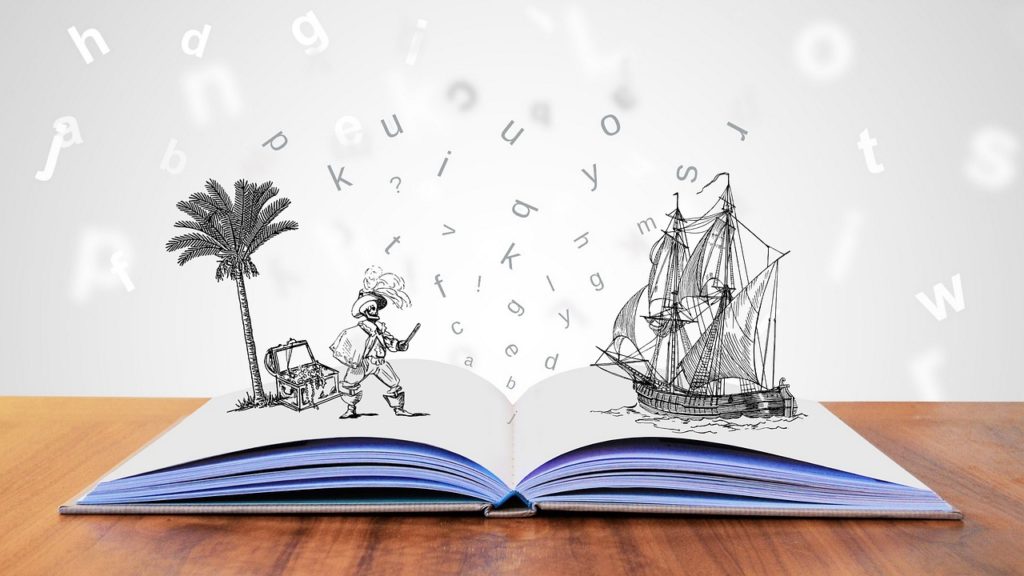
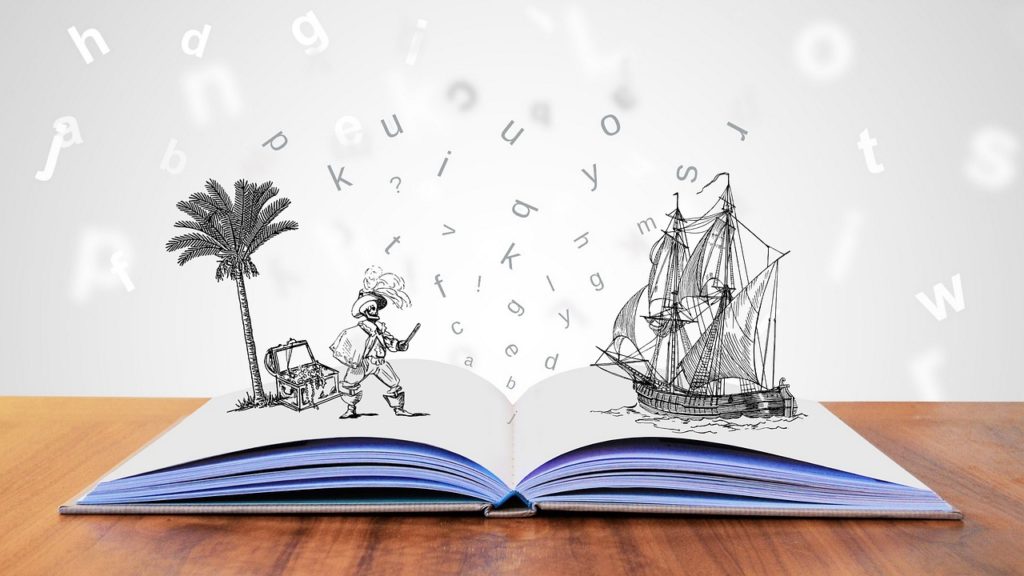
教訓が得られるドキドキ・ハラハラのストーリー。
森の中にお母さんヤギと7匹の子ヤギが住んでいました。お母さんは町へ買い物に行く時に子ヤギに狼が来てもドアを開けてはいけない事、ガラガラ声、黒い手には気を付ける事を伝えます。
暫くするとドンドンとドアを叩く音がします。「お母さんだよ、開けておくれ!」と言っていますが、声はガラガラ声でした。子ヤギたちは狼だと気づきドアを開けませんでした。そして狼は家に帰り声を綺麗にする薬を飲みました。
またドアを叩く音がして「お母さんだよ。開けてちょうだい」と綺麗な声が聞こえます。しかし、窓から覗く手を見ると真っ黒。子ヤギたちはドアを開けませんでした。狼はまた家に帰り手に白い粉を付けました。
そしてドアを叩く音がして綺麗な声で「開けてちょうだい」と言っています。手も白いです。子ヤギたちはドアを開けてしまいました。開けてみるとそこには狼がいて、子ヤギを次々と食べてしまいました。
お母さんヤギが帰ると時計台の中に一番下の子ヤギが隠れて生きていました。そして、二匹は狼を探しに出かけると野原でいびきをかきながら寝ている狼を見つけました。
よく見るとお腹が動いていて、子ヤギたちはお腹の中で生きているようです。そしてお母さんは狼のお腹をハサミで切り、代わりに石を詰め込みました。
ようやく目が覚めた狼はあまりのお腹の重さに上手く歩けず、井戸に真っ逆さまに落ちてしまいました。
緊張と緩和のストーリー展開が楽しめるグリム童話の有名作です。


こんな方におすすめ


以下の項目に当てはまる方に「おおかみと7ひきのこやぎ」はぴったりの絵本です!購入を検討してみましょう。
- 話を聞く大切さを感じられる絵本を探している
- 展開ややり取りが面白く、展開を予測しながら楽しめる絵本を探している
絵本比較!あなたに合った絵本を探そう!
「おおかみと7ひきのこやぎ」は探している絵本とは違った…。そんなあなたにはこちらをおすすめ!
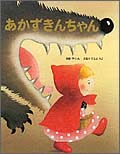
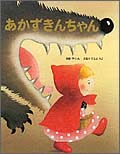
ドキドキの展開の中にある教訓「あかずきんちゃん」
誰もが一度は聞いたことがあるグリム童話の名作。起承転結がしっかりとした分かりやすいストーリーの中に話を聞く大切さなどの教訓が織り交ぜられています。
「おおかみと7ひきのこやぎ」よりも分かりやすい展開で、似たような教訓が感じられる絵本を探している時におすすめの一冊。
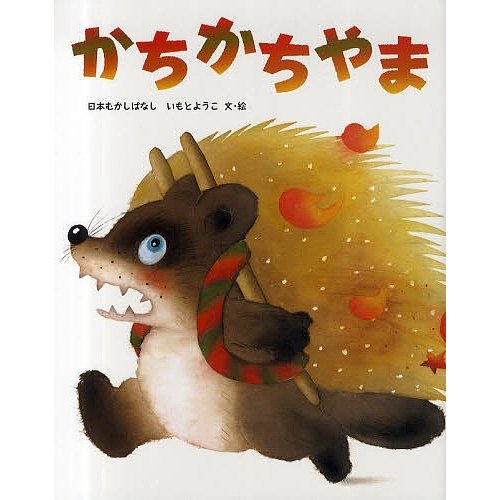
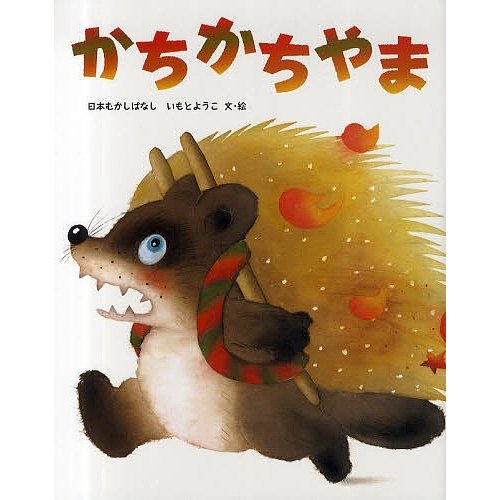
因果応報が感じられる教養として知りたい日本昔話「かちかちやま」
日本の有名な昔話の1つ。お婆さんを騙したり、叩くなどの行為をしていた狸がお婆さんを慕っていたうさぎに仕返しをされるお話し。他者への関わり方を考えさせられる一冊です。
因果応報ということがより強く感じられ、善悪の判断についても考えられる絵本を探している時はこちらをおすすめ。
目的・ねらい


絵本はそれぞれ作者の願いや思いが込められています。その思いを汲み取り、絵本を読むときに目的やねらいを持つ事をおすすめします。以下の「目的・ねらい」はRyuが読み聞かせをするときに大切にしている事です。参考にしてみてください。
- 他者の話を聞いた方が良い事もあるという事を感じる
- 展開を予測しながら、絵本や物語の面白さを知る
目的・ねらい1
楽しい中に教訓が詰まっています。
「おおかみと7ひきのこやぎ」は母親とのやり取りやストーリーの中で約束を守る事の大切さ、話を聞くことの大切さ、疑う事の大切さなどが感じられます。
昔話ということもあり、押しつけがましい教訓をイメージしがちですが、本作はそのような事はなくあくまで物語を楽しむ中で教訓のようなものが感じられるようになっています。
押しつけがましくないので「絶対に言う事を聞かなければいけない」というよりも「話を聞いた方がいいこともあるんだ」ぐらいの感覚で教訓を感じる事ができます。
目的・ねらい2
純粋に展開が楽しく、物語や絵本の魅力に気付ける作品!
目的・ねらい1で書いたような教訓的なものもありますが、「おおかみと7ひきのこやぎ」は最後まで聞き手の心を離さない展開が大きな魅力の1つ。
少しの怖さや緊張感、予測しやすい展開、言葉のやり取りの楽しさなど絵本や物語の魅力がぎゅっと詰まっています。
これまで絵本や物語に興味を示さなかった子であっても、その楽しさに気付けるような面白さがあるので絵本・物語に興味や関心を示すきっかけとなり得る一冊でもあります。
チェックポイント


現場で毎日読み聞かせを行う現役保育士が、実際に何度も読み聞かせをしたことで分かった大切なポイントを見ていきましょう。
| 年齢 | 幼児期、特に4歳児 |
| 季節 | 一年中 |
| 行事 | 発表会など |
対象年齢
幼児期以降がおすすめです。
文の量や最初から最後まで繋がりのある展開などを考えると幼児期でないと最後まで集中できない可能性があります。また、狼が襲ってくるという怖さもあるので、幼児期でも4歳児頃に読む事をおすすめします。
4歳児頃になると狼と子ヤギのやり取りの楽しさや展開を予測する楽しさも十分に感じられるようになっている事が予測されるので、「おおかみと7ひきのこやぎ」の魅力が最大限伝わるでしょう。
時期・季節・行事
少しの恐怖やドキドキを楽しいと感じている様子が見られた頃がおすすめです。
例えばおばけに関する絵本を見て恐怖だけしか感じないようでしたら、本作を読むのはまだ少し早いです。おばけや狼など恐怖を象徴するようなものを見てドキドキはするけど楽しみもある、現実と空想の区別がついてきた頃に読みましょう。
ただ恐怖しか感じない時に読んでも「おおかみと7ひきのこやぎ」もただの怖いだけの作品になってしまう可能性があるので、「あかずきんちゃん」や「めっきらもっきらどおんどん」などの少しの怖さもある作品が楽しめるようになってから読むことをおすすめします。
季節や行事感はありませんが、発表会などの演目にしやすい展開のある作品なので、子どもが興味を持ったら劇形式で楽しむのもおすすめです。
読み聞かせのポイント


「おおかみと7ひきのこやぎ」を読み聞かせをする中で意識しているポイントです。読み方を少し意識するだけで内容がぐっと伝わりやすくなります。読み聞かせをする中で自分なりのポイントも探してみるのも面白いですよ。
- 聞き手の反応を見て間を調整しながら読みましょう
- 感想を聞いたり、教訓を伝えるのは止めましょう
ポイント1
言葉と言葉の間を意識するとドキドキが増します。
狼がヤギたちの家に入ろうとする場面でのやり取りが非常に魅力的で、聞き手を引き込みやすいポイントです。聞き手も一番反応を示す場面なので聞き手の様子をよく見ながら読み進めていきましょう。
狼が「開けておくれ」と言った後や子ヤギたちが顔を見合わせる場面、ドアを開けようとしてしまう時、ついにドアを開けてしまう前などに少し間を空ける事で「どうなってしまうんだろう」と聞き手に感じさせることができます。
また、言葉のやり取りも楽しい場面なので、狼は少し低く、子ヤギは高くなど声の変化も少し意識すると臨場感が生まれて世界観を作る事ができるのでおすすめです。
ポイント2
大人の思いを押し付けず、それぞれの思いを大切に。
「おおかみと7ひきのこやぎ」は確かに教訓的な部分もあり、大人が「子どもに話を聞く大切さを感じて欲しいな」と思いながら読むこともあるかと思います。
思うのは自由ですが、それを聞き手に押し付けてしまうのは避けた方がいいでしょう。話を聞く大切さ、悪い事は返ってくる事など、本の持っているメッセージに大人は目が行きがちですが、子どもは思わぬ所に目をつけていたり、様々な感想を持っていたり発見をしています。
本作を通してどんな事を感じても聞き手の自由。感想を聞いたり、教訓を押し付けず聞き手の感じたままの事を大切にすることが大切です。
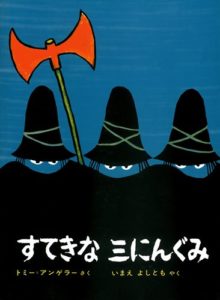
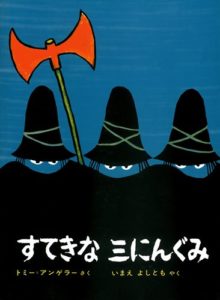
まとめ・Ryuの感想


グリムの中でも特に気に入っている一冊です。
展開が面白く、その中に学びや気付きが自然と含まれている作品。個人的にではありますが、とても好きな絵本です。
聞き手の反応も非常に良く、狼と子ヤギとのやり取りの場面は「きゃー!」「ダメダメ!」と言って、絵本の世界に入り聞き手も一緒になってドキドキしている事がよく分かります。
また、読み手としても工夫のし甲斐がある作品で、どのようにしたら更に聞き手が楽しめるのかを考えながら読む事ができます。聞き手の反応を見ながら読み方を工夫できるので、読み手のスキルアップにも繋がる絵本です。
教訓や学びとしての側面もありますが、展開が面白いので堅苦しくないのも魅力的。展開が楽しめる物語としても、学びがある絵本としてもおすすめできる一冊です。
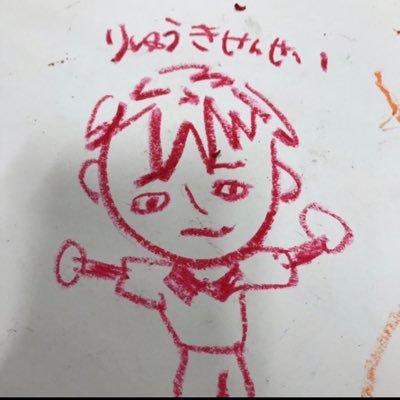
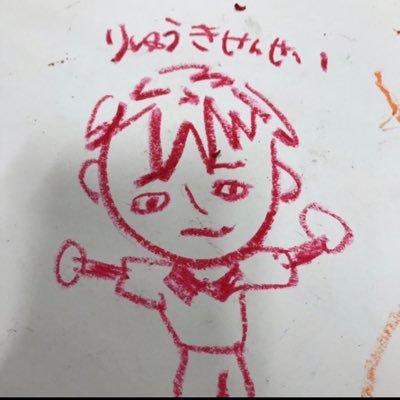
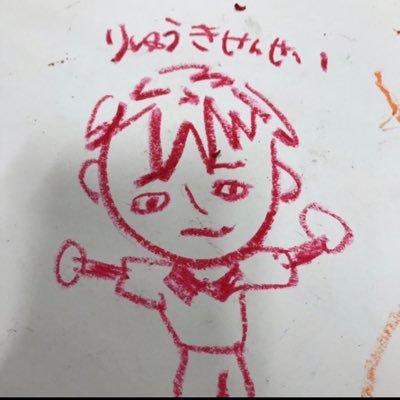
記事を書く励みになります。ポチっとお願いします!